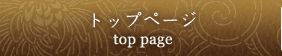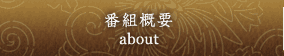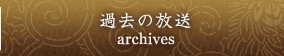過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年9月27日
佐渡 黄金の道〜日本海に浮かぶ宝の島〜

日本一の金山として栄えた佐渡島。江戸時代に金を運んだ相川街道を辿ります。
中世から残る港町では昔、巨大な北前船を建造していました。
また旅で出会ったのは佐渡名物のたらい舟に乗って行われる昔ながらの漁でした。
そこで獲れたばかりの新鮮な海の幸をいただきます。
金山の豊かさから生まれた芸能の数々。
鬼太鼓と呼ばれる激しい太鼓と踊りや、夜の闇に薪の灯りに照らされた幻想的な薪能を紹介します。

宿根木(港町)
江戸時代は北前船の舟大工の里として栄えた港町。入り江の狭い地形に密集する町並みや石畳の路地が当時の面影を残している。

佐渡国小木民族博物館
復元した原寸大の北前船が展示されていて実際に乗ることもできる。
住所:新潟県佐渡市宿根木270番地2
TEL:0259-86-2604

妙宣寺
妙宣寺は日蓮の弟子が自宅を寺として開基した日蓮宗佐渡三本山のひとつ。妙宣寺の五重塔は日光東照宮を模した木造・純和風の高さ24.11メートルの五重塔。親子二代で30年の年月をかけて建築した。国重要有形文化財。

相川(鉱山町)
相川は江戸時代「ゴールドラッシュ」に沸いた。全国各地から鉱山技術者や商人、労働者たちが集まり、それまで百姓の寒村だった島に突如人口5万人とも言われる大都市が誕生した。その相川の京町通は今も和風建築の家が並び当時の面影を残す。

佐渡金山 道遊の割戸
1601年の金脈の発見により、人の手で掘り進められた露天掘跡。山自体を斧で割ったかのようなその異形は、佐渡金銀山遺跡の象徴となっている。
住所:新潟県佐渡市相川宗徳町

佐渡奉行所
江戸幕府の遠国奉行の職名の一つ。奉行は老中支配に属し、勘定奉行の指導をうけ、金銀山の管理と島内13万石の民政を主な役目としたが、江戸後期は外国船の監視など、海防も重要任務となった。
佐渡奉行所には金や銀を精製する工場、勝場(せりば)があった。鉱石をこなごなに砕いて細かくして水で流しながら金銀と泥や岩とを分別する猫流しと呼ばれる施設が造られた。そこで見張り役を務めたのが猫場のおばあちゃん、ねこ場婆。ネコババの語源になったといわれる。

花の木
2,000坪の敷地の中に古い民家を移築して、宿坊離れに5室と古民家の中に2室ある。150年前の民家を移築・復元した母屋。有名なミュージシャンが宿泊して作曲したことで知られる。
住所:新潟県佐渡市宿根木78-1
TEL:0259-86-2331

茶房やました
宿根木の一角にある古民家の喫茶店「茶房やました」。たらい舟をさかさまにしてテーブルになっていたり。2階には北前船に積まれていた船箪笥が飾ってある。船箪笥は引き出しの奥にスペースがあってお金が隠せるようにしてあり金庫の役割をしたという。また万が一、船が沈没した時のために水に浮くように造られている。

佐渡たらい舟
江戸時代に始まった「たらい舟漁」。味噌樽を半分に切ったようにみえるこの舟は「はんぎり」と呼ばれ味噌樽職人が造っていた。昭和30年代頃までは、島の北側一帯では嫁入り道具の大切な一品だったが現在では観光用になっていて小木港で乗ることが出来る。

鬼太鼓おんでこ
佐渡の鬼太鼓は約500年前佐渡に伝わったものといわれ、能の舞に各地の特色ある洗練された太鼓と独特の振り付けがされ、現在の鬼太鼓の形が完成したもの。島全体では120組はあると言われている。鬼太鼓は悪魔を払い、商売繁盛、五穀豊穣を祈って 神社の祭礼に奉納されるもの。 また、太鼓の打ち方は「しだら打ち」といい淒まじい形相をした鬼が裏太鼓に合わせて身を震わせ髪を振り乱し必死に太鼓を打つ姿は凄絶、真に迫るものがある。

無名異焼(むみょういやき)
無名異焼(むみょういやき)は、佐渡金山の坑中から算出される鉱土「無名異」を原料として、200有余年焼き継がれている佐渡固有の焼き物である。
江戸・天保年間から続く赤水窯は、無名異陶芸の始祖といわれる伊藤家が開いた伝統窯。初代・赤水から引き継がれてきた伝統を今に繋ぐのが、五代目となる伊藤赤水氏は人間国宝である。
住所:新潟県佐渡市相川一町目1
TEL:0259-74-2127

能
佐渡には今でも30以上の能舞台がある。佐渡に能が伝わったのは大久保長安がきっかけを作ったと言われている。大久保長安は徳川家康の側近で金山の開発のために佐渡を訪れた際、二人の能太夫を同行した。大善神社には島の中でも数少ない茅葺屋根の能舞台がありいつでも見学できる。
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.