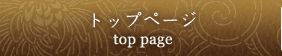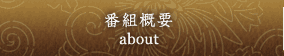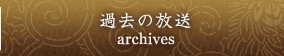過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年7月12日
信州越後・谷街道〜小布施からはじまる名湯の道〜

谷街道は松代、須坂、飯山の各城下町や小布施などを宿場として
飯山からは新潟の十日町街道と接続して日本海の海産物などの物資が多く運び込まれました。
今回は、栗の産地で知られる小布施を出発して、渋、湯田中、野沢などの名湯をめぐり
おいしいお米の産地で知られる魚沼、十日町までを巡ります。

小布施
小布施は北信濃にあって千曲川東岸に広がる豊かな土地で千曲川の舟運が発達した江戸時代には、交通と経済の要所として栄えたといいます。定期的な市「六斎市」がたち、川と川が合流して人や物が集まる場所という意味で「逢う瀬」と呼ばれていたことが現在の地名の由来と言われています。

岩松院(がんしょういん)
岩松院は葛飾北斎や俳人小林一茶ゆかりの寺でもあり、境内には一茶が「やせ蛙まけるな一茶これにあり」という句を詠んだ蛙合戦の池がある。
また本堂の天井には北斎が肉筆で描いた見事な「八方睨み鳳凰図」がある。

地獄谷
国の天然記念物に指定されている「渋の地獄谷噴泉」。絶えず100℃近い温泉を噴き上げていて渋温泉へも供給されている。
そのそばには地獄谷野猿公苑があり、世界でも珍しい猿が温泉露天風呂に入る様子をみることができる。

野沢温泉
8世紀の前半、行基が発見したと伝えられる野沢温泉は無料で入れる13の外湯が点在している。中でも野沢のシンボル的な温泉「麻釜(おがま)」は90度近い熱湯が湧き出す豊かな源泉で国の天然記念物。今でも村の人たちが野沢菜や玉子などをゆでるのに使用され「野沢温泉の台所」といわれていて生活の場所になっている。
(写真は野沢の外湯がある通り)

健命寺
野沢温泉の健命寺は、宝暦6 年(1756)頃に、当時の住職が京都に遊学した際に、京都の天王寺蕪の種を持ち帰り栽培をしたことがはじまりだとされている。その種を寺の庫裡裏の畑にまいたところ、蕪が小さく葉柄が大きい天王寺蕪とは違ったものが育ったという伝説が残っている。
住所:長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9320
TEL:0269-85-2063

星峠
日本古来からの美しい棚田の田園の風景が広がる星峠。ドラマやCMで度々紹介されていて、その美しい風景をカメラに収めようと、日本全国から多くの人がやってくる名所となっている。

歴史の宿 金具屋
明治38年創業の桜肉(馬肉)を扱う老舗。
渋温泉の老舗旅館「金具屋」。昭和の初めに建てられた木造4階建ての日本情緒あふれる斉月楼は国の登録無形文化財。廊下を温泉街の道に見えるようにして、宿泊客が旅館の中でも旅を楽しめるようにした工夫されている。宮大工が長年培った技術の粋を結集した伝統軸組構造の建物は釘や金具はほとんど使われていない。
住所:長野県下高井郡山の内町平穏2202
TEL:0269-33-3131

よろづや
湯田中温泉の旅館「よろづや」。「桃山風呂」は、まるで寺院の中に風呂があるかのような作りで美肌の湯が自慢。
外にはまるで池のような庭園大露天風呂があり自然と歴史が織り成す露天風呂は絶景。
住所:長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3137
TEL:0269-33-2111

小布施堂本店
小布施堂本店は和風の伝統の栗菓子をいただくことができる。定番は栗鹿ノ子、その他、その月限定で出されるメニューは四季折々の目にも美しい生菓子でここに来てしか食べることができない。
住所:長野県小布施町808
TEL:026-247-2027

桝一市村酒造場
宝暦5年(1755)に創業した桝一市村酒造場。店内には“手盃台”(てっぱだい)と呼ばれる和風のカウンターがありそこで、おちょこ一杯から全銘柄を味わうことができる。
ここで働くセーラ・マリ・カミングスさんはアメリカ・ペンシルベニア出身ながら欧米人初の利酒師。
住所:長野県小布施町807
TEL:026-247-2011

うぶすなの家
大正時代に建てられた古民家だったが大地の芸術祭をきっかけに陶芸作品などが展示されている美術館であり、また地元のおかあぁんたちが料理を出してくれるレストランでもある。
住所:新潟県十日町市松代3743-1 まつだい「農舞台」内
TEL:025-595-6688
(越後妻有 「大地の芸術祭の里」総合案内所)
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.