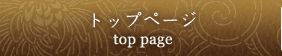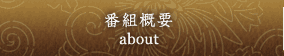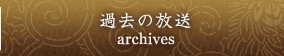過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年4月12日
日光街道〜職人の技息づく参詣道〜

江戸日本橋から北へ。徳川家康を神として祀る日光東照宮への『参詣の道』、日光街道。
山間を行くこの道は、江戸時代の活気を残す「足立市場」の競り風景や、
東照宮の造営にかかわった匠の技・桐たんすなど、
粋でいなせな職人たちの息吹を宿す道。
今回は、江戸から続く職人たちの技と心意気をもとめ、日光街道を旅します。

足立市場(あだちしじょう)
430年前にできた千住の青物市場、通称「やっちゃば」がその始まりといわれる。昭和20年に水産物専門の市場となり、江戸・東京の台所を賄ってきた。市場内の食堂は一般客も利用でき、月に1度(不定期)の「足立市場の日」にはここで「ねぎま鍋」を振舞うことも。見学の申し込みも受け付けている。
住所:東京都足立区千住橋戸町50
TEL:足立市場の日について…03-3879-2750
(足立市場協会)
足立市場見学について…03-3882-4301
(足立市場業務管理係)

越谷梅林公園
越谷は古くから梅の名所として知られ、2万2千m²の公園内に、約40種類、300本あまりの梅が植えられている。
住所:埼玉県越谷市大林203-1
TEL:048-963-9225(越谷市公園緑地課)

旧篠原家住宅
宇都宮を代表する旧家の一つ。江戸時代から醤油醸造業や肥料商を営んでいた。大谷石を用いた蔵(文庫蔵)は江戸時代1851年の建築、母屋は明治28年の建築で、国の重要文化財に指定されている。
住所:栃木県宇都宮市今泉1-4-33
TEL:028-624-2200

大谷景観公園
2千万年前の火山活動により生まれた、大谷石(おおやいし)。宇都宮北西部の大谷地区が主な産出地で、約1500年前の大谷石の石棺が発見されるなど、古より採掘、利用されてきた。大谷景観公園はかつての採掘地で、大谷石の岩壁が連なる奇観を一望できる。
住所:栃木県宇都宮市大谷町1224

カトリック松が峰教会
スイス人建築家、マックス・ヒンデル氏の設計により、昭和7年創建。ロマネスク様式の本格的な聖堂で、外壁・内壁ともにそのほとんどが大谷石作り。信者以外でも、聖堂・敷地内の散策可。
住所:栃木県宇都宮市松が峰1-1-5
TEL:028-635-0405

草加せんべい「いけだ屋」
江戸時代、「おうめだんご」という屋号で街道の茶店を営んでいたが、江戸末期の慶応元年(1865年)、せんべいを主とした商いに移行。こだわりの炭火手焼せんべいは、草加近郊のうるち米をセイロで蒸し、天日で干し、備長炭で1枚1枚焼き上げた、自慢の一品。
住所:埼玉県草加市吉町4-1-40
TEL:048-922-2061

鮒の甘露煮「ぬた屋」
江戸時代、古河を流れる渡良瀬川やその周辺の湖沼などでとれた鮒を、醤油で煮て保存食にしたのがはじまり。尾頭付きの鮒を、たっぷりのざらめ、水あめ、和三盆で煮詰めた甘露煮は、縁起物として今も親しまれる郷土料理だ。
住所:茨城県古河市中央町3-8-5
TEL:0280-22-4127

春日部桐たんす「飯島桐箪笥製造所」
「春日部桐たんす」は、江戸時代に日光東照宮の造営のため、全国から集まった腕利きの工匠の一部が、桐が豊富にあった春日部に滞在したことから始まる、といわれる。今も、昔ながらの天日干しで「原木の渋抜き」を行い、釘を一切使わずに組み立てるなど、匠の技にこだわり、守り継がれている。
住所:埼玉県春日部市豊野町1-1-9
TEL:048-734-3922
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.