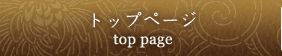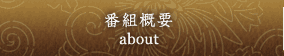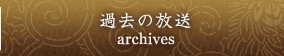過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年4月5日
山陽道〜世界遺産・厳島神社へ 瀬戸内の美食めぐり〜

瀬戸内海の沿岸を東西に走る山陽道は、畿内と大宰府を結んだ古代からの大路です。
広島県・三原から、かつての安芸国へ。
江戸時代の人々は日本三景「安芸の宮島」、そして世界遺産・厳島神社を目指し、街道を歩きました。
街道沿いでは、瀬戸内海の恵みが豊かな食と暮らしをもたらしました。
海の恵みを味わいながら厳島神社へと、山陽道を旅します。

かき船 かなわ
江戸時代、広島の牡蠣を大阪の河岸まで船で運んで直売したのが「かき船」だ。後に船内で牡蠣料理を出すようになったという。「かき船」の風情と、牡蠣の味わいを存分に楽しめる。
住所:広島県広島市中区大手町3丁目平和大橋東詰
TEL:082-241-7416

石風呂温泉 岩乃屋
(いしぶろおんせん いわのや)
瀬戸内海に面した山すそに、岩を掘りぬいた岩風呂で、日本古来の蒸し風呂だ。岩の天井を熱し、海水に浸した海藻を敷き詰めた風呂は、「あつい方」(室温60〜90℃)と「ぬるい方」(室温40〜60℃)がある。海藻の薬効が昔から伝わっている。
住所:広島県竹原市忠海床浦1丁目12-30
TEL:0846-26-0719

厳島神社(いつくしまじんじゃ)
世界文化遺産。創建は推古元年(593)で、平安後期の仁安3年(1168)に、平清盛が廻廊を配した寝殿を造営した。本社祓殿、高舞台などが国宝となっている。
住所:広島県廿日市市宮島町1-1
TEL:0829-44-2020

岩惣(いわそう)
宮島の弥山(みせん)のふもとに建つ、安政元年(1854)創業の老舗旅館。初代が紅葉谷に茶屋を設けたのがはじまりで、夏目漱石、森鴎外など明治の文豪が愛した。紅葉谷川に沿って、5棟の離れがある。
住所:広島県廿日市市宮島町南町345−1
TEL:0829-44-2233

うえの
瀬戸内海は古くから穴子が捕れ、特に「宮島の穴子」は有名だった。江戸時代に丼飯で食べられていたが、宮島口に鉄道が敷かれると、駅弁「あなごめし」が誕生した。穴子のアラからとった出汁で炊き込んだ飯に、焼き穴子がぎっしり。
住所:広島県廿日市市宮島口1-5-11
TEL:0829-56-0006

一国斎高盛絵(いっこくさいたかもりえ)
一子相伝の漆塗りの技で、植物や昆虫といったモチーフを、漆で高く盛り上げて描き出すのが特徴。発祥は尾張だが、広島へやって来た職人から技が受け継がれ、花開いた。
広島県産業政策課 産業企画グループ
TEL:082-513-3355
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.