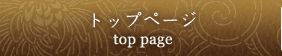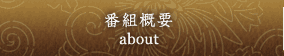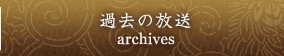過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年6月7日
東海道〜琵琶湖から京都へ 美しき水めぐりの旅〜

東海道、大津から京都に至る終の道のりは、大津港に集まる物資を都に運ぶ要路でした。
日本最大の湖・琵琶湖から古来より清流に恵まれ栄えた京都洛中へ。
美しい水の景色の中で出会うのは、水が育てた旬の味覚です。
江戸時代の旅人は、京都の夏の風物詩・納涼床で極上の夕涼みを楽しみました。
初夏の緑を楽しみながら、水の道を旅します。

石山寺(いしやまでら)
奈良時代の開かれた寺院。山の中の大きな石の上に本堂が建っていることが名前の由来。境内の頂上から北を見下ろせば琵琶湖の絶景。花や池も美しい、1000年以上前から愛される景勝地でもある。平安時代には宮中の女性たちの間で「石山詣で」が流行し、紫式部はこの場所で「源氏物語」を書き始めた。後の時代にも、松尾芭蕉・島崎藤村などがここで作品を残している。
住所:滋賀県大津市石山寺3丁目2−28
TEL:077-537-1105

琵琶湖疎水
平清盛、豊臣秀吉ら天下人は琵琶湖の水を京都に引き活用することを望んだが、当時の技術では叶わなかった。京都の長年の夢を適えたのは、明治23年、大学を卒業したばかりの技術者・田邉朔郎。浄水場や水力発電所を京都にもたらした。京都の文明開化の立役者であるこの水路沿いを歩けば、レンガのトンネルなどのモダンな景色を楽しめる。
住所:京都市上下水道局 疏水事務所
TEL:075-761-3171

下鴨神社(しもがもじんじゃ)
平安京が置かれるより遥か昔よりある神社。水の神様を紀元前より祭る。1年を通して数々の有名な祭りがあるが、夏の一大イベントは土用の丑の日に行われる「みたらし祭」。江戸時代、「みたらし池」という鴨川の伏流水が湧き出た池で禊をするために、多くの人が夏の東海道を旅したと言われる。
住所:京都市左京区下鴨泉川町59
TEL:075-781-0010

鴨川納涼床(かもがわのうりょうゆか)
鴨川沿いにある料理屋・旅館などが河原に置いた床5月から9月はこの上で食事を楽しめる。現在99軒の店が納涼床を出す。一説によると出雲阿国(いずものおくに)が四条河原(しじょうがわら)で歌舞伎を披露していた頃より始まったとされる。暑い京都の夏、旅人を川風でもてなす場所。

幾松(いくまつ)
鴨川沿いに立つ江戸末期の建物が料理宿になっている。政府登録国際観光旅館。桂小五郎と幾松が暮らした部屋があり、食事客、宿泊客は事前に希望すれば、歴史の話を交えながら部屋を案内してくれる。納涼床もあり、夏は夕涼みをしながら鱧や鮎などの会席を楽しめる。
住所:京都市中京区木屋町御池上る
TEL:075-231-1234

総本家 ゆどうふ 奥丹清水
創業377年の湯豆腐店。「昔どうふ」と自称する豆腐は、ニガリ含め全て手作り。石臼を使い、大豆と水を絶妙なバランスで挽き、豆の美味さを最大限に引き出す。湯豆腐は最初の一口を何もつけずに食べるのがおすすめ。お出汁やネギを少しずつ足して味の変化を楽しめる。
住所:京都市東山区清水3丁目340番地
TEL:075-525-2051

京焼・清水焼団地共同組合
山科の西部に清水焼団地という住所があり、ここには京焼・清水焼の作家の工房、窯元などが密集している。茶の湯が広まり、戦国時代より上流階級のニーズに応えた茶碗を作ってきたのが京焼のルーツ。多様かつ高度な焼き物の技がここに集まる。
TEL:075-581-6188(京焼・清水焼団地協同組合)
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.