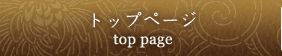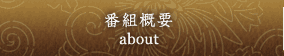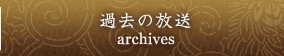過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2012年1月12日
金毘羅街道〜心弾む こんぴら参りの道〜

江戸時代、庶民の信仰を集めた讃岐国のこんぴらさん。
お伊勢さんと同様、当時「一生に一度のこんぴら参り」は
庶民たちの大きな楽しみのひとつだった。
今回は、こんぴら船で賑わった岡山の下津井から、塩飽本島を経て、香川の丸亀に上陸。
かつての面影を残す街道沿いに琴平町へといたる旅。
名物の長い石段を昇り、酒に芝居にお土産探し…
良き時代の「旅の楽しみ」に満ちた街道を歩いていきます。

むかし下津井回船問屋(むかししもついかいせんどんや)
下津井は、かつて大阪から四国をめざすこんぴら船の寄港地として賑わった。また、北前船の港としても栄え、当時通りには20軒を超える廻船問屋が軒を連ねていた。江戸時代の廻船問屋を復元したこの施設は、さまざまな資料を展示しながら、海とともに暮らしてきた人々の歴史と文化を伝えている。
住所:岡山県倉敷市下津井1-7-23
TEL:086-479-7890

塩飽勤番所(しわくきんばんしょ)
瀬戸内海に浮かぶ塩飽諸島は、古くから海運で知られる塩飽水軍の本拠地だった。江戸時代、幕府の御用船方となった島の人々は、領地を与えられ、独自の自治制度により自らを治めていた。塩飽勤番書はその政庁跡。信長、秀吉、家康。3人の天下人たちが船方衆に宛てた朱印状が残されている。
住所:香川県丸亀市本島町泊
TEL:0877-27-3540

丸亀街道(まるがめかいどう)
港町丸亀から、こんぴらさんに続くおよそ12キロの道。四国には、島内のさまざまな地域からこんぴらさんに至る5つの大きな街道があり、中でも丸亀街道は、本州から渡ってくる参詣者で最も賑わった。街道沿いには、今も当時の道標や石灯籠、茶堂跡が数多く残されている。

善通寺(ぜんつうじ)
弘法大師空海が自身の生誕の地に開いた寺院。父・佐伯善通(さえきよしみち)の名から善通寺と名づけられた。高野山、東寺と並び弘法大師の三大霊場のひとつとされる。広い境内には多くの堂塔が立ち並び、大師を祀る御影堂のほか、産湯につかったと伝えられる産湯井(うぶゆのい)も残されている。
住所:香川県善通寺市善通寺町3-3-1
TEL:0736-56-2011

金刀比羅宮(ことひらぐう)
象頭山の中腹に新座する、庶民信仰の神さまを祀る神社。祭神は大物主神と崇徳天皇。古くは海の神、航海の守り神として信仰されていたが、江戸時代にはさまざまな願いごとを叶える「こんぴらさん」として親しまれ、広い信仰を集めた。今も年間300万人の参詣客が訪れる。
住所:香川県仲多度郡琴平町892-1
TEL:0877-75-2121

こんぴらうどん
こんぴらさんの表参道にあるうどん店。水気を切ったつゆなしのうどんに、特製しょうゆをかけて食べる「しょうゆうどん」が名物。
住所:香川県仲多度郡琴平町810-3
TEL:0877-73-5785

丸亀うちわ(まるがめうちわ)
江戸時代にこんぴら参りの土産物として始まり、以来、地場産業として大きく発展した。現在も日本のうちわの9割が丸亀で生産されている。
住所:香川県丸亀市港町307-15(うちわの港ミュージアム)
TEL:0877-24-7055
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.