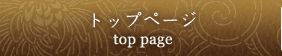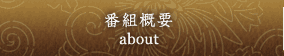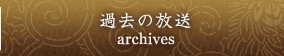過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2011年11月17日
千国街道〜北アルプスを望む塩の道〜

千国街道は太古から開かれ、明治までの重要な輸送路。
この道が取り分け重視されたのは、江戸時代。
松本藩は太平洋側からの塩の移入を禁止し、日本側から運ばれる「北塩」のみ認めました。
北塩の多くは千国街道経由でもたらされ、松本平に暮らす人々にとって、
この街道は生命線だったのです。
その流通を担ったのが、夏は牛方(うしかた)、冬は歩荷(ぼっか)。
千国宿辺りを境に、急な坂道が続く北部では、山道に強い牛が使われ、
冬の豪雪時は、歩荷(ぼっか)が活躍した街道でした。

田鹿麩店(たじかふてん)
安政年間創業の焼き麩専門店。越後では冬の越冬食として古くから食され、歩荷さんのお弁当のおかずにもなったという。
住所:新潟県糸魚川市寺町1−1−21
TEL:025−552−0203

牛方宿(うしかたやど)
1人で牛6頭を追って一人前と言われた牛方が疲れを癒した宿。牛方が牛といっしょに寝泊りした宿。こうした宿は、千国街道に何軒かありましたが現存する唯一が沓掛集落の牛方宿。江戸末期の建物で間口6間、奥行10間、当時の民家としては、柱の太さや本数、仕組みなど質の高い建物。
住所:長野県北安曇郡小谷村千国乙840
TEL:0261‐71‐5610

穂高神社(ほたかじんじゃ)
祭神は、穂高見命(ほたかみのみこと)、綿津見命(わたつみのみこと)など三柱で、社伝によると
穂高見命が穂高岳に降臨した。諏訪大社と共に信濃三社で崇敬。9月26‐27日の「御船祭」では、舟形の山車が練り、安曇野が海の民によって作られた事を今に伝える。
住所:長野県安曇野市穂高6079
TEL:0263−82−2003

菊之湯(きくのゆ)
松本藩の奥座敷と言われた浅間温泉は数々の文人墨客が逗留した名湯。菊之湯は本棟作りの民家形式で、浴槽はイタリー産大理石を用いた菊風呂、伊豆石と御影石の赤風呂など。
住所:長野県松本市浅間温泉1‐29‐7
TEL:0263‐46‐2300

わちがい
元々、江戸時代の大庄屋だった栗林家の旧宅で、大町の典型的な京風町屋造り民家。店名は当時の屋号に由来し、地元の食材と地酒にこだわった創作料理が堪能できる。
住所:長野県大町市上仲町4084
TEL:0261−23−7363

新橋屋飴店(しんばしやあめてん)
江戸時代から、松本はお米と水に恵まれ、あめ屋が30数軒あったと言われ、砂糖を使わず、米と麦芽のみで甘みを出す昔ながらのあめ屋。
住所:長野県松本市新橋3−21
TEL:0263−32−1029
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.