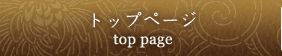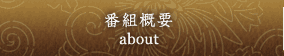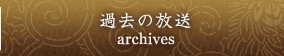過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2011年9月8日
長崎街道〜異国の風が薫る道〜

九州、長崎と小倉を結ぶ長崎街道。
江戸時代の鎖国で、唯一海外との窓口となった長崎・出島。
そこに異国からの驚きの文化が数多く到来しました。
それらはこの街道を通じて京、大坂、江戸へと渡って行きました。
異人が歩き、象が通り、舌をとろかせる砂糖が運ばれる道。
未知の世界を求めて若き志士たちが目指した道。
長崎街道はまさに好奇の心と新たな世界を結ぶワンダーロードだったのです。
開国、明治維新へとつながる日本の夜明けは、長崎と、この街道なくては語ることができません。
象が渡った橋、西洋の科学に取り組んだ湯の里、異人たちが感嘆した冥境の峠、
和と洋が綾なし、異国の風が薫る長崎街道を旅します。

常盤橋(ときわばし)
九州の玄関口、五街道の起点・終点で、その重要さから九州における日本橋に位置づけられていた。当時のままに木製の橋が再現されている。西詰の室町界隈はかつての商店・旅籠が並んだところ。この橋を江戸へ向かう将軍献上の象が渡った。何日も前からの場所取りなど物見の群衆で大賑わいだったという。
住所:福岡県北九州市小倉北区室町2
TEL:0186-63-0111

蘭学館(らんがくかん)
武雄鍋島家28代領主、鍋島茂義は長崎警備の任を通じて西洋の進んだ科学に感銘を受け、蘭学の導入に熱心に取り組んだ。武雄市の蘭学館には、日本初の西洋式大砲、日本初の牛痘、医療用ガラス器の製作、写真技術の研究など様々な分野に及んだ当時の資料が展示され、茂義の進取の志を今に伝えている。
住所:佐賀県武雄市武雄町大字武雄5304-1
TEL:0954-20-0222

冷水峠(ひやみずとうげ)
西の箱根と呼ばれた長崎街道髄一の難所。日差しも届かないうっそうとした山道が続く。途中にある地蔵堂脇に渓流が流れ、その水の冷たさが名の由来とか。江戸参府でここを通った偉人たちも、この沢水で喉を潤したであろう。1612年頃の開墾とされ、山道には当時の名残りを留める石畳が続いている。
住所:福岡県飯塚市内野と筑紫野市山家に跨る峠

料亭 青柳(あおやぎ)
長崎の花街、丸山町で200年の歴史を持つ卓袱(しっぽく)料理料亭。木造の家屋は築100年を越える。幕末の英傑、大隈重信、井上馨も訪れたという。
住所:長崎県長崎市丸山町7番21号
TEL:095-823-2281

梅ヶ枝荘(うめがえそう)
長崎は大村の名物「大村寿司」を供する。別名シュガーロードとも呼ばれる長崎街道。出島を通じて到来した砂糖は、日本の食文化に大きな影響を与えたが、ここ大村のちらし寿司はすし酢に大量の砂糖を使った伝統の味。
住所:長崎県大村市玖島1丁目36(大村公園内)
TEL:0957-52-3523

香蘭社(こうらんしゃ)
300年の歴史を持つ有田の窯元・陶器商。八代目が明治初期、カンパニーを立ち上げ、万国博覧会出品などで評価を高め、有田の焼き物の海外進出を展開させた。歴史を経たコレクションが展示されている。
住所:佐賀県西松浦郡有田町幸平1-3-8
TEL:0955-43-2131
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.