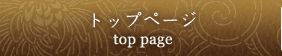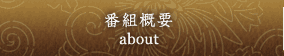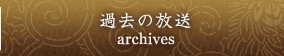過去の放送
2012年9月放送
2012年8月放送
2012年7月放送
2012年6月放送
2012年5月放送
2012年4月放送
2012年3月放送
2012年2月放送
2012年1月放送
2011年12月放送
2011年11月放送
2011年10月放送
2011年9月放送
2011年8月放送
2011年7月放送
2011年6月放送
2011年5月放送
2011年4月放送
2011年12月29日
平戸街道〜島々が織りなす絶景の道〜

九州最西端の長崎県平戸市から、佐世保市を縦断し、長崎街道へとつながる平戸街道。
出発点となる平戸は、出島ができる前、日本最古の海外貿易の拠点となった城下町。
そして、208もの島々が浮かぶ佐世保の海は、
江戸時代から「九十九島(くじゅうくしま)」と呼ばれた景勝地です。
今から約450年前、世界への扉が大きく開かれた平戸。
今回は、島々が織りなす絶景と異国の香りをもとめて、平戸街道を旅します。

平戸島/平戸城
平戸藩松浦氏の居城。天守閣からは遠く壱岐まで望むことができ、眼下には大航海時代に外国船が行き交った平戸港とその海が広がる。また、城に隣接する亀岡公園では、樹齢400年を越えるマキの並木が江戸時代当時のまま残っている。
住所:長崎県平戸市岩の上町1458
TEL:0950-22-2201

生月島/平戸市生月町博物館 島の館
江戸時代に日本最大規模を誇った捕鯨の展示をはじめ、豊かな自然の中で営まれた漁業や農業など、生月島の歴史・文化を展示、紹介している。
住所:長崎県平戸市生月町南免4289
TEL:0950-53-3000

江迎(えむかえ)本陣/潜龍酒造
元禄元年より続く造り酒屋。平戸街道の整備により、参勤交代の折りに平戸藩主が宿泊する本陣屋敷を務めた。10代藩主・松浦煕が名づけた御成りの間「枕水舎」の他に、殿様御使用の厠・湯殿なども復元され、当時の様子を知ることができる。見学は事前に予約が必要。
住所:長崎県佐世保市江迎町長坂209
TEL:0956-65-2209

石橋/御橋(おはし)観音寺
10代平戸藩主・松浦煕が選んだ「平戸八景」の一つ。高さ20m・全長27mの石橋は壮大。九州八十八ヶ所の75番札所である仏教寺院「御橋観音寺」の境内奥にあり、春は桜、秋は紅葉の名所としても知られる。
住所:長崎県佐世保市吉井町直谷94

九十九島(くじゅうくしま)
九十九島とは、佐世保市沿岸25kmに連なる大小208の島々のこと。「九十九」とは「数え切れないほどたくさん」の意味で、江戸時代中期よりこの名で呼ばれ、景勝地として親しまれていた。
住所:長崎県佐世保市船越町2277(石岳展望台)
TEL:0956-22-6630(佐世保観光情報センター)

黒島天主堂
明治35年、信徒たちの献金と労働奉仕で完成。祭壇に敷かれた有田焼のタイル、木目を本物そっくりに描く「櫛目引き」など、細部にこだわった装飾は見ごたえあり。国指定重要文化財。ミサなどの宗教行事以外は、一般公開もしている。黒島へは佐世保市相浦港からフェリーでおよそ50分。
TEL:0956-22-6630(佐世保観光情報センター)

平戸蔦屋
1502年創業、平戸藩の御用菓子司を務めた老舗菓子屋。平戸藩主の命により、江戸時代の菓子100種類をまとめた『百菓之図』の製作にかかわる。カステラをベースにした百菓の一つ「カスドース」は、今も平戸蔦屋の銘菓として伝わる。
住所:長崎県平戸市木引田町431
TEL:0950-23-8000

食事処ふくべ
江戸時代、日本最大規模の捕鯨を誇った生月島。鯨の皮を炒めるときの「じりじり」という音からついた「じりじり鍋」など、伝統の鯨料理を食すことができる。
住所:平戸市生月町山田免1993−6
TEL:0950-53-0185

黒島どうふ
黒島で祝いの席にのぼる郷土料理、黒島どうふは、昔から家庭でつくる「お母さんの味」。大釜で大量に大豆を炊き、海水を"にがり"として豆乳を固めるのが特徴。
TEL:0956-22-6630(佐世保観光情報センター)

三川内(みかわち)焼
400年以上の歴史を持つ焼き物の里、三川内。江戸時代は平戸藩の御用窯として、殿様のために贅を尽くした器を焼いていた。純白の磁器と細かい細工が特徴。1830年頃から、「ヒラド」の名でヨーロッパに輸出され、今も17軒の窯元が伝統の三川内焼を製作している。
住所:長崎県佐世保市三川内本町343(三川内陶磁器工業協同組合)
TEL:0956-30-8311
Copyright© BS-TBS, INC. All rights reserved.