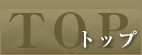
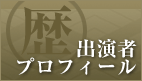
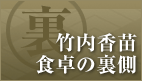

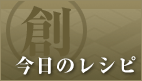
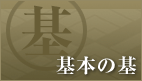
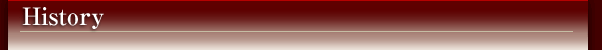
|
The History of 海老 6月15日放送 (# 36) |
|||
海老というのは種類が非常に多く、世界中で約2800種類が生息していると言われています。そのうち日本では食べられているのはわずか約20種類。 |
 |
||
海老は日本では縄文時代から食べられていました。古い文献でいうと、「出雲風土記」(733年)に海老の記述があります。 室町時代以降は武家の婚礼の宴にイセエビが欠かせないものとなったようです。 おめでたい赤色、それにヒゲを伸ばし、腰が曲がっていることから長寿が連想され、海老と祝宴が結び付けられたと考えられます。しかし、一般の庶民には縁遠いものでした。 そして江戸時代、やっと伊勢海老以外のエビが登場してきます。 江戸前(東京湾)でクルマエビ、芝エビなどが獲れる様になり、寿司・天ぷらに使われようやく庶民の口にも徐々にエビが入るようになりました。 明治の初期になると日本に西洋文化が入ってきます。 |
|||
東京銀座に今でもある高級レストラン「煉瓦亭」にエビフライが登場したのが最初で、ここから全国に広まって行ったといわれます。しかし、当時は12銭で高嶺の花。まだまだ家庭では食べられないものでした。 |
 |
||
日本人が海老を本格的に食卓に取り入れたのは1961年以降輸入の自由化から。このころ、中国から盛んに輸入されたのが大正エビです。 自由化を機に、価格も下がり高度成長に伴って、供給・消費ともに拡大し、人気食材となりました。 しかし、人気がありすぎて数が足りなくなるという問題も…。そこで1946年海老の養殖技術が確立します。 1964年、山口県秋穂町で、世界で初めて産卵・孵化からの養殖技術を確立したのが「車えびの父」こと藤永元作博士。 この博士の養殖技術は海を渡り台湾のブラックタイガー養殖技術へとつながりアジアから養殖エビが日本へどっとはいってくるようになった、という事です。 |
|||