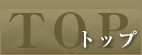
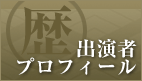
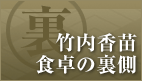

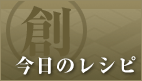
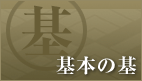
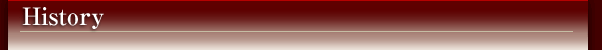
|
The History of 鰹 5月11日放送 (# 31) |
|||
<世界での歴史> |
 |
||
<日本での歴史> |
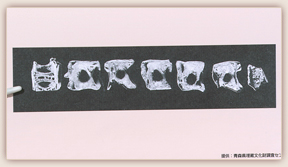 |
||
718年の「養老律令」には、このように「堅魚(かたうお)」「堅魚煎汁(かたうおいろり)」という言葉があり、カツオが重要貢納品に指定され、貴族が食していた事を物語っています。当時は生で食する習慣はなく、茹でた後に干した物を献上しており、これが現在の鰹節の原型といわれています。 |
|||
【「堅魚煎汁」とは、鰹を煮た後の煮汁をさらに煮詰めたもの。うま味が濃縮され、醤油が発達する前は、この鰹の調味料が重宝されていました。 |
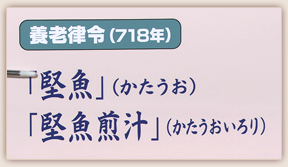 |
||
そして鎌倉時代に入ると、魚介類を取引する「イサバ商」が登場し、魚介類の生産と消費が一気に増大!生で鰹を食べる習慣もこのころには一般化しました。
ところが鎌倉時代も後期に入ると、鰹はあまり食べられなくなってしまいます。何故なら、鰹は足が早く、腐りやすいので生食に合わず、あまりいい魚ではないとみなされてしまうのです。 しかしその後、鰹の復活の歩みが始まるある出来事が起こります。時は1537年。戦国時代の武将、北条氏綱(うじつな)が鰹釣りの見物をしていました。するとそこに一匹の鰹が氏綱の船に飛び込んできたのです。これを見た氏綱は「戦に勝つ魚が舞い込んだ」と大喜び!そしてすぐさま出兵した戦で実際に勝利をおさめました。この話が武士の間でたちまち広がり、以来縁起の良い魚としてあげられるようになりました。 さらに縁起を担ぎ鰹節を「勝男武士」と漢字であてることも。 そして江戸時代になると、鰹はさらに時代の花形となるのです。
この鰹縞(かつおじま)の着物を着流すことがイキだと言われるほど鰹にスポットが当てられていました。
また、鰹にまつわる川柳も読まれています。 「女房を質に入れても初鰹」 「女房を質に入れても食べたい」といわれるほど江戸っ子は初鰹に対するこだわりがあったんです。 しかし、明治時代から海の濁りなどから鰹が序々に南下し、湾にいなくなってしまいます。当時鰹漁は七反帆と呼ばれる帆船で行われており、あまり沖には出られなかったので漁獲が減少してしまいます。 しかし、明治39年、静岡県で富士丸という動力船が進水。それをきっかけに鰹の漁場が沖合いまで拡大し、鰹漁は再び黄金時代を迎えた魚なのです。 |
|||