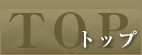
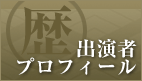
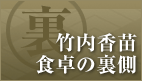

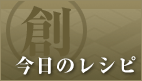
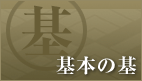
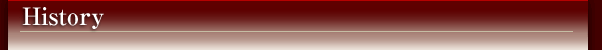
|
The History of 羊 6月1日放送 (# 34)人類の歴史に貢献した羊たち |
|||
「羊」が家畜化されたのは約1万1千年前。西アジアや中央アジアに棲んでいた野生のムフロンが飼育されるようになったのが始まりと言われています。 |
 |
||
遊牧民の移動によって各地に広まっていきました。 時は流れ、12世紀末。当時スペインで誕生したスパニッシュメリノという品種の羊は、最も繊細で優美な羊毛を生産する羊とされていました。当時、このスパニッシュメリノの独占生産で、羊毛王国として栄えたスペインのイサベラ女王の援助があって、 |
|||
コロンブスは航海に出られたといわれています。そして、1492年、コロムブスがアメリカ大陸を発見。「羊」はスペインの船で新大陸へ、南アメリカや北アメリカに連れて行かれました。 |
 |
||
同じ頃、イギリス(大英帝国)も羊毛を使った毛織物の生産国へと発展を遂げ、それで蓄積した富で、さらに毛織物の機械の改良や発明が産業革命へと続いていきます。 こうして「羊」は、世界中に広まったのですが、日本に本格的に「羊」が入ってきたのは、明治時代以降のこと。鎖国がとかれ、西欧文化の輸入とともに、羊毛製品の需要が拡大しました。 その後、日清・日露戦争、そして第一次世界大戦で軍服や毛布など羊毛の軍需的資源としての必要性が認識され、政府は国防上の理由から「めん羊100万頭計画」を策定、本格的にめん羊に飼育に乗り出した。 |
|||
そして、第二次世界大戦後は食糧難と物不足の時代。日本のめん羊飼育頭数と飼育戸数の変遷を見ると、羊飼育熱は高まり、昭和32年には史上最高の944,940頭を記録するに至った。 |
 |
||
しかし、この頃の「羊」の飼い方というと、1農家に1.5頭程度という飼い方で採算がとれず、外国から安い羊毛や化学繊維が入ってくるようになって国産の「羊」は激減します。そして、90万頭以上いた「羊」が20年間で1万頭足らずになってしまいました。 |
 |
||
必要なくなった「羊」は食肉業者にこぞって引き取って貰い、それが安いマトンとして、市場に大量に出回りました。しかし、本来羊毛をとるための羊を長期間に渡って食用としたため、年老いた羊が出回り、羊肉は硬い・臭い・不味いというイメージがついてしまいました。 そして、平成17年度の時点で全国の「羊」の飼育頭数はたったの8,650頭しかないのが日本の現状なのです。 <日本での羊肉の種類> ラム…生後1年未満の子羊肉 マトン…1年以上たった羊肉 ホゲット…マトンのうち1年以上2年未満 ※国によって違います |
|||