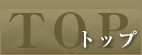
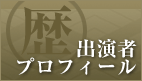
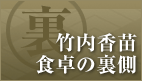

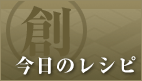
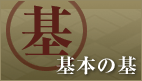

|
12月1日放送 (# 8) |
|||
「蕎麦はいつからあなたのソバに?」 |
|||
もともと蕎麦は今のような麺ではなかったのをご存知でしたか? 蕎麦の起源は中国の雲南省と推定されており、四大文明の地域でも紀元前4〜5千年頃に栽培されていました。日本にも、すでに縄文時代には渡来しており、最古のものは北海道渡島のハマナス遺跡から出土しています。ということは、日本人は縄文前期頃には蕎麦を食べていたことになるのです。 当時は今のような麺ではなく、粉にして練って作る「蕎麦練り(蕎麦がき)」や「蕎麦団子」にして食べていました。 |
 |
||
ところが! 江戸時代になると、小麦粉をつなぎに使う方法が朝鮮から伝わってきました。その結果、蕎麦は麺として急速に普及していったのです。当時は「そば切り」と呼ばれたそうです。そして、「そば切り」は簡単に作れ、サッと食べられることから、17世紀半ばの江戸の町にはこんなものが登場しました! そう、蕎麦の屋台です。 |
 |
||
江戸時代には蕎麦のほかにも寿司や天ぷらの屋台もあったそうで、今でいうファーストフードの走りですね。この蕎麦屋台、せっかちな江戸っ子に受けに受けて、大流行しましたが、火災の原因になるとして、幕府が禁止した為、姿を消してしまいます。 |
 |
||
さあ、そこで問題です! |
 |
||
今も庶民に親しまれている蕎麦ですが、自給率はわずか20%以下。中国、アメリカ、カナダからの輸入に頼っているのが現状です。
|
|||