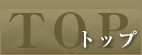
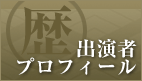
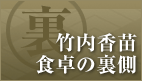

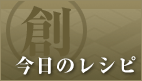
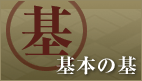

|
3月30日放送 (# 25) |
|||||||
〜「シラウオとシロウオの違い」〜 |
|||||||
|
|||||||
シラウオは現在青森県小川原湖で1番とれています。 |
 |
||||||
<シラウオの説明> |
|||||||
それを聞きつけたのが徳川家康は、もともと三河で獲れるシラウオが好物だったため、「万代の吉兆である」と大喜び。シラウオを徳川家に献上させたそうです。 |
 |
||||||
家康在世中、シラウオは“御止魚(おとめうお)”と呼ばれ、将軍の御膳に供えるほかは、みだりに漁はできませんでした。その漁を唯一許されたのが、森孫右衛門を頭とする漁師たち。
1950年代頃から隅田川の汚染が進み始め、シラウオの姿を見ることは難しいくなりましたが、毎年3月1日に木箱に入れた北海道産のシラウオを献上する行事は今でも残っています。 <海外では…> シラウオは英語で「Icefish」と呼ばれており、海外でも食べられています。 生息域はロシアから中国、朝鮮半島。特に中国と朝鮮半島では食べられているようです。 中国では「鱠残魚」と書き、言い伝えによると、中国の呉の国の王が大河を船で行く途中に、お正月に食べる鱠(なます)の残りを川に捨てたところ、それが化けてシラウオになったので、この名が付いたそうです。 韓国ではキムチと一緒に煮込んだり、塩辛にして良く食べられているそうです。 |
|||||||