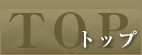
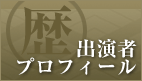
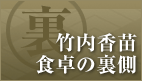

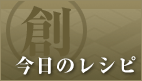
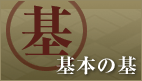

|
2月23日放送 (# 20) |
|||
〜ほう、レンソウだね!?〜 |
|||
<ほうれんそうってどんな漢字?> 「菠薐草」と書いて「ほうれんそう」と読みます。 このことから、二つのことがわかります。 |
|||
一つは、ほうれんそうは中国から入ってきたということ。 |
 |
||
<伝播ルート> 原産地ペルシャから、ほうれんそうはどう世界に伝わっていったのか?この伝わり方によって、東洋種と西洋種の2種類のほうれんそうが出来上がったのです。 一つは、7世紀にシルクロードを通って中国へ伝わり、栽培され、東洋種のルーツになりました。それが、17世紀初期に日本に伝わりました。この頃は、唐から伝わったということで「カラナ」と呼ばれていました。 もう一つ、ヨーロッパへ伝わった西洋種のルートは、1800年代にフランスから日本に入ってきました。 |
|||
世界の生産国ベスト5は、 |
 |
||
<東洋種と西洋種の違い> 東洋種は葉先がとんがっていて、切れ込みが深い。アクが少なく歯切れがよいため、おひたしのような和風の料理に向いています。 西洋種は葉に丸みがあり、葉柄が太い。アクが強く葉肉が厚い。バター炒めなど、高熱をかける料理に向いています。 因みに、“ポパイがほうれんそうを食べて強くなる”という設定は、アメリカのほうれんそうはアクが強くて、子供たちに不人気だったことから生まれたといわれています。 現在口にしているほうれんそうは、東洋種でも西洋種でもない、交雑種というものが主流。東洋種のような甘みがあってアクが少なく、西洋種のように病気に強くて、通年収穫できるという、両方のいいとこどりをしたものなのです。 <ほれんそうの旬> 旬は冬。冬寒くなると凍えないために、自分のなかに養分をためこむという生体反応がある為、ビタミンCの量が最も高くなるのが冬なのです。 糖度は、通常6度くらいですが、冬だけ栽培・収穫される「ちぢみほうれんそう」の糖度は10度を越えています。 |
|||
つまり、甘味もビタミンCも、最も高くなる冬が、ほうれんそうの食べごろというわけです。 |
 |
||