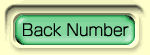2001年8月4日放送 マーケット・ナビのポイント
1. 実質GDP成長率(前年同月比)
1997〜98年の通貨危機が去った後、世界あるいは米国の「ハイテク生産基地」として急速に景気回復を図ってきたアジア諸国、特にNIEs各国は、昨年後半以降のITブームの崩壊により米国経済が急激に落ち込んできた煽りをモロに受け、現在、深刻な景気低迷に喘いでいる。世界各国の経済がグローバル化の進展で連関を深めた結果、米国景気の悪化は、NIEs諸国のみならず、日本・欧州・イマージング市場をも直撃し、さながら「世界同時不況」の入り口に差し掛かっているという感がある。
今週は、特にIT関連産業の集積度が高い台湾・シンガポール・韓国に焦点を絞り、「米国発のIT不況」を概観してみる。
グラフは、3カ国の四半期ごとの前年同期比実質GDP成長率をプロットしたもの。シンガポールは、昨年第4四半期に通貨危機後ピークの+11.0%成長を示現したのち、今年第1四半期に+4.5%に急減速、最近発表された第2四半期速報は▲0.8%とマイナス成長となった。
台湾は2000年第1四半期の+7.9%がピークで、今年の第1四半期は+1.1%で1975年第1四半期来の低成長となった。
韓国は、99年第4四半期の+13.0%が成長の頂点で足許の今年最初の四半期は+3.7%と減速気味であるが、他2国と比べると比較的堅調を保っている。
2. シンガポール実質GDP成長率(前期比年率)
前掲3カ国のうちシンガポールの成長率を前期比年率でみると、今年第1四半期が▲11.3%、4〜5月のデータに基づく速報ベースで第2四半期が▲10.1%と、主に米国経済についてエコノミストが簡便的に用いるリセッションの定義(2四半期連続でマイナス成長)に当てはまる結果となった。これを受け、シンガポール政府は2001年の成長見通しを従来の+3.5〜+5.5%から、+0.5〜+1.5に大幅下方修正した。因みに、98、99、2000年の年次成長率は、それぞれ+0.1%、+5.9%、+9.9%。
カギとなる鉱工業生産の底入れの兆しが全く見られないことから(前年同期比で、4月▲0.7%、5月▲10.6%、6月▲16.1%)、米国経済の動向次第では、2001年はマイナス成長となる可能性は低くはない。
3. 世界の半導体販売額(前期比年率)
アジア経済減速の主因は、前述の通りITブームの崩壊である。特に、コンピュータや携帯電話の世界的な需要減速は、世界のチップ生産基地となっていたNIEs諸国を直撃している。グラフは、世界の半導体販売額の前年同期比の推移であるが、2000年中頃には50%を超える驚異的な拡大を見せていたのが、今年2月からマイナスに転じ、5月には▲20%と大幅な減速を見せた。特に半導体需要の多くを占める携帯電話の世界需要の回復見通しは暗く、昨年度まで指数関数的に増加してきたのが一転して、出荷台数ベースで昨年度の4億8,000万台から3億9,000万台に大幅減少するとの予測もあることから、半導体販売の一層の調整は不可避であろう。
4. 各国の輸出構造
IT関連財の対米輸出を起爆剤に急速な回復を見せてきたNIEs諸国であるが、逆にその回復過程を支えた経済構造そのものが、皮肉なことに現在の景気急後退の主因となっている。更に、内需の浮揚に失敗した日本がNIEs諸国に似通った景気回復戦略をとっており、同様に米国ITバブル崩壊の波に飲み込まれたため、NIEs諸国にとって事態は一層深刻である。
主題ではないが、日本について付言すれば、アメリカへのCentralizationを裏の顔として持つGlobalizationの進展が、日本をアジアのローカル・エコノミーにおとしめたという感が強い。
5. 各国の対米輸出(前期比年率)
グラフは韓国・シンガポール・台湾の対米輸出額の前年同期比を3ヶ月移動平均で平滑化したものである。昨年半ばから大幅な減速を示していることが分かるが、これが各国経済低迷の主因であることは、前述の通りである。
今年に入ってからの平滑化前の推移を下表に示したが、韓国は7月に▲20.0%、台湾が6月に▲16.9%、シンガポールが5月に▲22.6%、6月に▲16.6%となるなど、昨年の驚異的な伸びがあるだけに、足許の下落の勢いは生半可ではない。
6. ドル・円相場推移
今週のドル円相場は、週初大きくドル高が進んだものの、米国景気の楽観論を退ける経済統計が発表されたことで、週後半は円が買われる展開になった。
参議院選挙での自民党大勝を受けて迎えた週初30日(月)は、小泉政権が構造改革に本格的に着手すれば一層のデフレは不可避であるとの見方が広がり、円売り・株売りの展開となった。ドル円は123円台の前半から125円台の前半まで2円近く上昇、日経平均はバブル後最安値を更新した。この日発表になった本邦6月の鉱工業生産指数が非常に悪かったことや、塩川財務相の「自然な円安は静観する」との発言も、ドルの買い安心感につながった。
翌31日(火)はポジション調整から一時124円台後半に弱含む動きを見せたが、ニューヨーク引け値では125円台を回復した。8月1日(水)は同日ニューヨーク時間に発表された7月のNAPM(全米購買部協会)製造業景気指数が、市場の予想以上に悪かったことを受けて米国景気の早期回復期待が後退、対ユーロ、対円でドルは値を下げた。ドル円は一時124円台前半に下落、ユーロ・ドルは一時5月来のレベルとなる0.8832まで上昇、ユーロ・円も一時110円台をつけた。
翌2日(木)は日経平均の大幅高(+439.87円、2週間ぶりに12,000円台回復)を手がかりに円を買い戻す動きが顕著となり、これに6月の米製造業受注が前月比▲2.4%と急減速を示したことで、米製造業者からのドル高是正の声が強まるとの見方から、ドル売りの流れが加速、ドル円は一時123.60をつけた。3日(金)の東京時間では、ドル円は123円台後半で推移している。
ドル高が米国経済回復を阻害しているという見方が急速に広がっている。米通貨当局が明示的にドル高政策を転換することは考えづらいが、設備投資の落ち込みを反映して資本流入が減少したり、内需減速で輸入が減少する傾向が続き、自然にドルが減価していく場合、通貨当局が静観を決め込むことはありうるだろう。ファンダメンタルズからは円売りというスタンスに変わりはないが、市場の目がドル安に向けられ始めている現在、遠くない将来の一時的な円高も想定しておく必要もあろう。
G-SECドル円指数はややドル高・円安を示す60.7(先週確値は53.6)、来週の予想レンジは121〜126円。