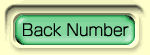2001年7月28日放送 マーケット・ナビのポイント
1. 日経平均株価指数
5月の連休中の14,500円超えをピークに、日経平均株価は下落基調を強めている。世界的なIT不況の煽りを受けたハイテク関連株およびIT関連素材関連を中心とした非鉄金属株、更に不良債権処理を「構造改革」の目玉に据えられた銀行株の下落が相場の下げをを先導している。先週18日(水)には3月14日以来となる12,000円割れを示現、今週23日(月)には今年3月13日につけたバブル後最安値を更新し11,609.63で引けた。これは16年前の1985年以来のレベル。
買いの材料が殆ど見つからない中、自立反発した局面では銀行の持合い株解消売りのインセンティブもあり、頭が非常に重い展開。銀行株については、不良債権処理に伴う損失が各行の予想を大きく上回るとの思惑や、9月中間期決算で完全実施される時価会計に伴い、株価下落が銀行の自己資本を大きく毀損するとの懸念が出ており、こうした見方が銀行株の下落を誘い、市場全体の下げをリードするという悪循環が見られる。
内閣府が7月9日に発表した試算によると、今年3月末の主要14行の株式含み損はおよそ2,700億円で、TOPIX指数は1,277であったが、TOPIXが10%下落(1,150)、20%下落(1,022)、30%下落(894)すると含み損はそれぞれ、1.99兆円、3.70兆円、5.42兆円に拡大するとのことであった。この試算が正しいとして按分計算をしてみると、現在のTOPIXのレベル(1,190近辺)では1兆円台前半の含み損ということになる。
2.日経平均とTOPIX
日経平均はバブル後最安値を更新したが、よりマーケット全体の動向を示すTOPIX指数で見ると下落幅は日経平均ほどきつくはない。グラフでみると99年前半から日経平均とTOPIXの乖離が大きくなっている。2000年前半に世界的なITブームで株価がピークを付けるまでは、中低位大型株中心の日経平均は、ハイテク値がさ株が相場を主導したTOPIXと比べ上昇が抑えられていたが、ニュー・エコノミー株が大きく下落し始めた後の昨年の4月に日経平均の大幅な銘柄入れ替えが行われ、TOPIX以上に日経平均が「ハイテク・ヘビー」になった結果、ITバブル崩壊のあおりをより直接的に受ける形となっている。つまり、上昇局面に上手く乗れなかっただけではなく、下落の影響はモロに受けるという、日経平均をインデックスに使っている運用者にとっては最悪のパターンである。因みに、昨年4月の銘柄入れ替えがなかったとして、日経平均を再計算してみると、16,000前後となる。
3.銀行株指数とジャパン・プレミアム
先週レポートした通り、先週、日経平均に先駆けて東証銀行株指数はバブル後最安値を更新した(上段グラフ)。下段のグラフは米ドル3ヶ月物のLiborで見たジャパン・プレミアムの推移であるが、98年の金融危機をはさんだ期間では、株価指数とジャパン・プレミアムは非常にきれいな逆相関をしていることが分かる。98年の金融危機は、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行、日本債権銀行といった大手行の破綻といういわばidiosyncraticな危機が金融全体のsystemicな危機につながった例であり、当時個々の邦銀の破綻が真剣に懸念され、短期マネー市場において邦銀は想像を絶する資金繰り難に直面していた。しかし、99年3月の公的資金注入後は、邦銀の破綻懸念はほぼ解消され、格付けの改善はなくとも、ジャパン・プレミアムはゼロに収束した(=短期マネー市場において、欧米プライム銀行とほぼ同等のレートで資金調達が可能となった)。この状態は、今年の株価急落局面においても変わっていない。
今後、株価の下げが更にきつくなれば、若干のジャパン・プレミアムを要求される局面が出てくる可能性もあるが、現時点でいえることは、足許の銀行株下落は個々の邦銀の資金繰り破綻懸念を反映したものでない、ということである。
4.米国GDP成長率(前期比年率)
米商務省が27日(金)に発表した今年第2四半期(4月〜6月)の実質GDP成長率の速報値は、前年同月比年率で+0.7%で、前月+1.3%(+1.2%から上方修正)を下回った。市場予想の平均値+0.9%をやや下回るレベル。
5.米国第2四半期実質GDP
内訳は最近発表された個別経済指標の結果を裏付ける形となった。
個人消費は堅調ながらも3%台から2%台の伸びに鈍化、相次ぐ利下げをサポートとした住宅投資は+8.5%から+7.4%と好調ながらもやや鈍化している。IT投資が急速に冷え込む中で、設備投資と輸出が大幅に落ち込み、それぞれ▲13.6%、▲9.9%となっている。
大きなプラスを維持しているとはいえ、IT景気減速のあおりを直接受けていない個人消費・住宅投資の動向が気になるところである。
6.ドル・円相場
今週は円やユーロ等の主要通貨に対して、ドルが弱含む動きが目立った。
先週末は、米国のドル高政策修正の思惑から123円台を割り込む水準までドルが売られた流れを受け、23日(月)は123円ちょうど近辺で寄り付いたが、オニール米財務長官の「強いドルを望む」との発言や日経平均がバブル後安値を更新したことを受け、ドルは124円台半ばまで上昇した。24日(火)にはドイツの7月消費者物価指数が市場予想比低かったことを受けて、ECBの利下げ余地が広がるとの観測から、ユーロが対ドルで上昇、一方米国株下落を嫌気したドル売りも出たことから、ドル円は一時123円台後半まで下落した。
25日(水)はFT紙に掲載されたオニール米財務長官の「なぜドルが高すぎると分かるのか。何と比較しているのか」との発言等でドル円は124円台前半まで上昇するも、ユーロが対ドルで一時0.88台まで強含むと、ドル売りの動きが強くなりドル円も123.50近辺まで下落した。26日(木)は、同日発表されたユーロ圏6月のM3が前年同月比+6.1%と大幅な伸びを示したことを受けてユーロが頭打ちとなったことや米国株式市場が値を戻したことを受けて、ドルの買戻しが先行、一時124円台を回復した。27日(金)の東京時間夕方現在、ドル円は123円台後半で取引されている。
ファンダメンタルズから見て円安を見ている市場関係者は多いが、米景気の不透明感が再び強まっていることを受けてドルが主要通貨に対して弱含みに推移していることもあり、目先はポジション調整の円の買い戻しが再び出てくる可能性もあろう。とは言え120円を再度割り込むことは考えづらい。
G-SECドル円指数はややドル高・円安方向の54.2(先週分の確報値は41.7)、来週の予想レンジは121円〜126円。