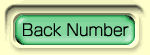2001年7月14日放送 マーケット・ナビのポイント
1. ユーロ・ドル相場
ユーロ圏景気の急速な悪化とECBの金融政策に対する不信感等で、6月下旬からユーロは値を大きく切り下げる動きを見せていた。先週末の7月6日(金)には、約8ヶ月ぶりとなる0.8350近辺まで下落した。
しかしながら、同日発表になった米6月の雇用統計が市場の予想以上に悪かったことでドル売り/ユーロ買いの機運が出て、この動きは週明け9日(月)、ジョージ英中銀総裁が「現在のドル高傾向には米国の景気にマイナス要素となる可能性がある」と述べたことで本格化し、ユーロは0.85台を回復した。
きな臭い動きを見せていたアルゼンチンを発端とする中南米経済不安であるが、10日(火)にアルゼンチンの3ヶ月物短期国債新規発行おいて、同国財政再建の遅れを嫌った市場が、2週間前を5%も上回る14%もの応札金利を付けにくるに及んで、ラテンアメリカ市場は株価や通貨の大幅下落に見舞われた。
最近のトルコやアルゼンチンの金融パニックは、他のイマージング・マーケットにさほど伝染しておらず危機感に乏しかったが、米国を先頭とした世界景気の減速が日増しに強まる中で、今週のミニ・パニックはラテン・アメリカ諸国のみならず、アジアから東中欧まで伝播、とくにポーランドやチェコの通貨が大幅に下落した。98年秋のロシア危機時にドルが大幅に下落した記憶もあり、ドル売り・ユーロ買いが進み、11日(水)には0.86台半ばまで買われた。12日(木)、13日(金)には0.85台で弱含んでいる。
今回の為替市場のユーロ買いの動きの背景には、「ファンダメンタルズでは日・米よりまだユーロ圏の方が有望」という見方が市場に依然根強くあることを感じさせた。
先月23日にこの番組で「ユーロ圏経済が低迷し始め、世界同時不況入りの観が強くなってきた」と述べたが、米国経済の減速感が強まれば強まるほど、消去法的にユーロ買いにつながる可能性も残されている。
2. 日・米・欧実質GDP(前年同月比)
グラフは日・米・ユーロ圏の四半期実質GDPの前年同期比伸び率推移。2000年第2四半期をピークに米国景気が急角度で減速する(2000年第2Q:+6.1%、2001年第1Q:+2.5%)のを受けて、ユーロ圏の成長率も米国よりは緩やかであるが、確実に鈍化している(2000年第2Q:+3.7%、2001年第1Q:+2.5%) 。
10日(火)のユーロ圏財務相会合の後の記者会見でレインデルス議長は、「2001年の成長率は2.0%〜2.5%になる」と述べ、それまでの+2.5%の見通しを下方修正した。
民間シンクタンク等の予想を平均すると、2001年度のユーロ圏の成長率見通しは+2%前後であるのに対し、米国は+1.5%前後、日本はゼロ近傍から若干のマイナス成長である。見通しレベルでは比較的にユーロ圏経済が優位にあることが分かる。
しかし、ユーロ圏はクローズドな経済圏ゆえ、世界特に米国経済の減速の影響は受けづらいとされてきたが、実際はドイツを中心に少なからぬ打撃を受けている。
3. 日・米・欧株式指数推移
日米欧の株価指数の動きを比べてみると、欧州株の下落が際立っている。欧州全域の優良企業300社の加重平均株価であるFTSEユーロトップ300指数は年初から14%近く下落しており、S&P500種指数の▲8.5%、東証株価指数(TOPIX)の▲2.7%と比べると下落幅が非常に大きい。
これは、底固いと思われていたドイツやフランスの企業の企業業績が急速に悪化していることに加え、外国人投資家のユーロ圏の構造改革に対する見方が悲観的になっていることによると考えられる。またドイツやフランス企業の売上げに占める北米市場の割合は2割に達し(欧州域外全体で35%)、米景気の減速が企業業績に与える影響は、経済指標に現れる以上に大きい。
4. 仏・独実質GDP(前年同月比)
ユーロ圏内でも国ごとの景況感の温度差は大きい。ユーロ圏12カ国のうち四半期ごとの国民勘定統計計算を行っていないギリシャ、ルクセンブルグ、アイルランドをのぞいた9カ国を、2001年第1四半期の実質成長率(前年同期比)順に並べると、3%台がスペイン・ポルトガル・フィンランド、2%台後半がフランス・オーストリア、2%台前半がベルギー・イタリア・オランダ・ドイツとなっている。
ここでは、比較的景気が底固いフランスと減速が最も激しいドイツの成長率を比べてみた。米国経済の成長と同期して、ドイツの成長率は2000年第2四半期に+4.0%にピークアウト、その後急速に減速して2001年第1四半期には+2.0%となった。一方、ユーロ圏の中で景気回復が速い方であったフランスは99年第4四半期の+3.8%がピークで、その後緩やかに減速しているが、2001年第1四半期でも+2.7%と比較的高い成長率をみせている。
2001年通年の成長率については、ドイツは+1%〜+1.3%程度、フランスは+2%を若干上回る程度と予想されている。ただし、これは年後半の米国経済の持ち直しを前提にしているという点には注意が必要だ。
5. 独・仏鉱工業生産(前年同月比)
グラフはドイツとフランスの鉱工業生産の前年同月比の推移。ドイツは2000年5月の+7.9%をピークを打った後、年末までは一進一退であったが、年明け後急速に悪化、4月に▲0.4%、5月に▲1.8%とネガティブ・テリトリー入りした。米国の鉱工業生産が前年同月比でマイナスになったのも今年の4月からで、米国経済との連動性が高いことが分かる。
一方フランスは若干弱含みながらも、4月時点で+2.0%と比較的堅調を保っている。
6. 独・仏消費者信頼感ID
一方、消費者心理はどうか。グラフは消費者信頼感DIをプロットしたものだが、年明け以降、両国とも下落傾向にあることは事実だが、ヒストリカルにはさほど低いレベルではない。これは、97年秋を底に両国の雇用環境が改善し、現在も好調を維持していることが背景にある。
失業率で見れば、97年秋のピーク時にドイツが11.8%、フランスが12.3%だったものが、現在ではドイツが9.3%、フランスが8.7%まで下がっている。しかしながら、企業収益の悪化が雇用や賃金に早晩影響を及ぼすことは容易に想像され、消費者マインドが一気に悪化していくことも十分考えられる。
7. ドル・円相場
ドル円は先週末126円台までドルが買われた流れを受け、125円台での週明けとなった。しかしながら、9日(月)のジョージ英中銀総裁の「現在のドル高傾向には米国の景気にマイナス要素となる可能性がある」との発言を受けてドルがじりじりと売られる展開になり、125円台前半まで弱含む展開となった。
さらに11日(水)に速水日銀総裁の「(今の為替の動きについて)行き過ぎた動きは必ず戻る。(円高傾向は)大丈夫だ」との発言や、アルゼンチンの問題が中南米諸国や東欧に広がりを見せ始めたことからドルは急落、一時123円台をつけた。米国政府高官からドルをサポートする発言がいくつか出たこともあり、124円台を回復したが、ドルが売られやすい展開が続いた。12日(木)には黒田財務官の「日本が構造改革を行っても経済のファンダメンタルズは必ずしも悪化しない」との発言が市場の円安見通しに疑問を抱いているととられたこと、引き続きイマージング・マーケットが荒れていること、同日発表の米国の新規失業保険申請件数が大幅に増加したこと等を嫌気し、ドルは一時123.51まで売られた。13日(金)の東京時間の夕方現在、124円台前半で推移している。
ファンダメンタルズから見て円安傾向が続く可能性が高いが、今回のアルゼンチン問題の行方によっては、大きくドルが売りこまれる可能性に留意したい。来週の予想レンジは122円〜127円。