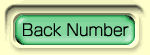2001年5月12日放送 マーケット・ナビのポイント
1. 欧州中央銀行政策金利の推移
欧州中央銀行(ECB)は5月10日(木)の定例理事会で、大方の市場の予想に反して政策金利である市場介入金利(リファイナンス金利)を0.25%引下げ、4.50%とした。ECBは99年11月に利上げを開始して以来、昨年10月までに合計2.25%の利上げを行ったが、年明け以降、日米が金利を下げる中、金利引下げに慎重な姿勢を崩していなかっただけに、市場には今回の利下げは大きなサプライズとなった。
2. 欧州中央銀行0.25%利下げ
ドイセンベルグECB総裁は、理事会後の記者会見で「今回の利下げは、中長期的なインフレ圧力が若干低下したことに対する金利水準の調整である。現時点で入手可能な情報からすれば、この金利の水準は、ユーロ圏経済が価格の安定を維持し、今後にわたって健全な経済成長に貢献するのに適切なものである」と語った。
金融政策の第1の柱であるマネーサプライ(M3:参照値は4.5%)については、「(マネーサプライの伸びにより)中長期的な物価安定が脅かされるリスクはない」と述べている。総裁は、直近3月のM3は前年同月比+5.0%と2月の同+4.7%と伸びが加速しているが、3ヶ月移動平均では+4.8%と参照値からかけ離れていないこと、非居住者による譲渡性証券の購入がM3に含まれており、これがM3を不当に押し上げていること等を指摘した。
第2の柱である物価の判断については、「物価安定に対する中長期的なリスクは幾分減少した」としている。その要因として、「海外環境の悪化で、ユーロ圏の成長率がモデレートしていることが、需要サイドからの物価上昇圧力を抑えている」こと、「ユーロ圏全体では、賃金の安定が保たれていること」等をあげている。
今回の利下げについては、(1)M3統計に含まれる撹乱要因を突然示して、利下げの正当化を行っていること、(2)今まで懸念材料としていた賃金動向に関して急に判断を変えたこと、等は非常に不透明な感じと失望感を市場に与え、実際、為替相場は利下げ後一瞬はユーロ買いに繋がったものの、直ぐに売りに押される形となった。
3. 米国労働生産性速報
5月8日(火)に発表された、2001年第1四半期の米非農業部門労働生産性(単位時間当り)速報値は、前期比年率で▲0.1%と市場予想(+1.1%前後)を大きく下回った。前期比マイナスとなるのは95年第1四半期以来6年ぶり。
2000年の第1四半期からの推移は、+2.1% ⇒ +6.3% ⇒ +3.0% ⇒ +2.0% ⇒ ▲0.1%となり、2000年第2四半期の+6.3%をピークにして大きく減速している。製造業の減速が主因であり、中でも耐久財製造部門の2000年第1四半期からの前期比年率の推移は、+13.9% ⇒+10.2%⇒ +11.5%⇒ +6.6%⇒ ▲0.1%と、2ケタ成長から一挙にマイナスの領域にまで落ち込んだ。
非農業部門全体の労働生産性前期比▲0.1%は、労働生産性算出の分子となる産出量が同+1.9%と伸びたのと同時に、分母となる総労働投入時間も同+2.0%と増えた結果である。レイオフが開始していたと考えられる本年第1四半期に、総労働投入時間が+2.0%と上伸していたことについては若干疑問が残るが、内数である製造業部門の総労働投入時間を見てみると、前月比▲6.0%と減少している(2000年第3四半期・第4四半期は、それぞれ▲2.8%、▲6.6%)。生産性上昇を主導してきた製造業部門における総労働投入時間の減少は、少なくとも足許では、それまでいわれてきた効率性の向上だけでなく、人員削減の影響も出ていると考えられる。非農業部門全体で総労働投入時間が増えたのは、結局、製造業以外の労働集約的部門における何らかの動きに影響されているはずであるが、その実態は、統計には明示されていない。
こうしたことを受けて、非農業部門全体の単位当り労働コストは前期比+5.2%と大きく上昇した。2000年第1四半期以来の推移は、+1.9% ⇒ ▲0.2% ⇒ +3.2% ⇒ +4.5% ⇒ +5.2%となった。一部では労働コストの上昇を通じてのインフレ・リスクを懸念する声も出てきており、気の早い向きは、スタグフレーションの可能性を示唆している。そこまでいわないまでも、今回の結果が、来週15日(火)のFOMCでの政策金利決定に影響を及ぼす可能性もないとはいえない。
4. 非農業部門の労働生産性
グラフは非農業部門労働生産性の前年同期比の推移。今年第1四半期は+2.8%となり、3期連続で伸び率が低下した。2000年第1四半期からの推移は、+3.8% ⇒ +5.3% ⇒ +4.8% ⇒ +3.4% ⇒ +2.8%。
トレンドを見ると、95年辺りから生産性の伸び率が高まっていることが分かる。実際、70年から94年までの平均値をとると+1.6%であるが、95年から2000年までのそれは+2.5%となり、実に1ポイント近く平均値が伸びている。この伸びこそが、90年代後半に米国がいわゆる「ニューエコノミー」入りしたとする大きな論拠とされてきた。
「ニューエコノミー」を支持する立場は、基本的に「高い生産性は永続的に維持される」と考える。一方で、95年〜2000年の高い生産性の伸び率は「単に景気がいいことによる」という景気循環論に基づく見方も根強くある。
経済のIT化が生産性向上に寄与してきたことは、近年の実証研究が明らかにしているが、ニューエコノミー派が、ITの貢献が主に「ITユーザ側」に現われたとするのに対し、景気循環派は、それが生産サイド、すなわち「IT生産側」へ与えた影響の方が大きいと考える。後者の見方は景気循環論と矛盾しない。
昨年の後半以降、景気の後退局面で生産性が下がって来ている事実があり、後者の見方に勢いがついてくると、ここ数年、盛んにもてはやされたニューエコノミー論が尻すぼみになる可能性がある。
5. 労働生産性と実質GDP
80年以降の非農業部門労働生産性と実質GDPとを並べてプロットしてみよう(いずれも四半期データの前年同期比)。一見して、両者の相関が低くないことが分かる。
相関係数を計算してみると、(1)80年第1Q〜直近:0.61、(2)90年第1Q〜直近:0.57、(3)95年第1Q〜直近:0.73となった。興味深いのは、労働生産性が底上げされた95年以降に、GDPと生産性の相関性が一段と高まっていることだ。無論、相関係数は二つの系列の因果関係を示すものではないため、「景気が良い(悪い)⇒生産性が高い(低い)」、「生産性が高い(低い)⇒景気が良い(悪い)」のいずれが正しいのかは、この分析からは判定できない。
しかし、少なくとも、ここ数四半期の様に、今後も下降局面で両者が相関を強めていけば、前ページで述べた景気循環論的見方がより有力になっていくことは、間違いない。
グラフからも見て取れるが、95年以前は労働生産性がGDPに僅かながら先行して動いていく傾向があったのに対し、95年以降はほぼ連動して動いていることが分かる。実際、80年第1Q〜94年第4Qまでの両者の相関係数は0.56であるが、GDPデータを1四半期分遅行させて、相関係数を計算しなおすと0.64とかなり大きくなる。一方、95年以降は、上記の通り、遅行系列をとらずとも、相関係数は0.73と高い。
このことは次のように説明できるだろう。即ち、景気(需要サイド)の動きに対し、生産量は比較的速く調整することが可能である一方、人員(労働投入量)の調整は一四半期ほどラグする傾向にあるということである。企業の行動パターンとしては当然のことであるが、ここで興味深いことは、95年以降は労働投入量も生産量とほぼ同期して調整される傾向が強まっている可能性が非常に高いということだ。
IT化との関連で、この最近の傾向を考えると、サプライチェーン・マネジメントの高度化で、企業活動のパラメターの変化をほぼリアルタイムで捕らえることが可能となったため、経営が、それまでは見極めが難しかった労働力調整を、いち早く行えるようになっているのではないか。言い換えれば、生産要素としての労働力の「物質化」が進展しているということだろう。
6. ドル円相場
ドル円相場は足許で120円〜125円のレンジに膠着しつつある。先週までは、小泉新政権発足で、「構造改革」期待から、海外勢の日本株買いが活発になり(外国人は連休の谷間の5月1日、2日だけで約4,300億円の買越し)、また米国の雇用統計や労働生産性指数等の経済指標が米国経済の減速を印象付けたことから、ドルは弱含みの展開を見せ、4日(金)には一時120.50まで下げた。
しかしながら120.00前後ではオプション取引に絡んだドルの防戦買いが大量に出ることが予想され、下値を追いづらい展開となっている。今週に入ると、海外勢の日本株買いの勢いはパッタリととまり、ドルが122円台までやや強含んでいる。とは言え、ドルの上値を追うエネルギーも見られず、結局、暫くは材料不足で膠着する展開が予想される。今週の予想レンジは、120円〜125円。