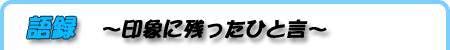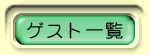
第240回 2005年7月30日放送

『トマト先進国』とはイタリアやギリシャのように料理に多くのトマトを使う国のことだ。では日本はというと・・・。これだけイタリア料理が流行り、食卓やお弁当の彩りにもトマトが使われ、その市場規模は2000億円とまで言われるものの、トマト先進国と比べると10分の1〜20分の1の消費量に過ぎないそうだ。まだまだ日本ではトマトは可能性を秘めているとも言える。 
日本で最も古くからトマトに取り組んできたのが『カゴメ』だ。創業は1899年、『トマト王』と呼ばれた故・蟹江一太郎氏が『愛知トマト』を起業し、トマトの栽培をスタートしたのが事業の始まり。もちろん、その前から日本にトマトは存在していた。すでに17世紀にはヨーロッパからトマトが伝えられてはいたが、当時は専ら観賞用で食べるものではなかった。そんな時代にあえてトマトの栽培に着手したのは、創業者の蟹江氏が軍隊にいた時、上官が口にした「これからの農業は西洋野菜だ」という一言からきている。西洋野菜の中でもいろいろな調理法のあるトマトに蟹江氏は注目した。まだ生のトマトがあまり受け入れられていなかったため、加工してトマトソースにしたものを販売した。 
時代は戦後、西欧文化が押し寄せ、学校の給食も洋食化しトマトソースの需要も伸びた。そして1933年にトマトジュースを発売したが、なかなか売れず廃棄処分の日々が続いたそうだ。トマトジュースが世間に認知されたのはそれから40年もあとのこと!黒柳徹子さんらを起用して、「お酒を飲んだ後はトマトジュース」のキャッチフレーズが人気となり、売上が伸び始めた。40年間もあきらめずにトマトジュースを売り続けた辛抱強さの賜物だ。1970年代には野菜ジュースを開始。現在、トマトジュースは市場シェア60%、野菜ジュースは65%を誇っている。 
バブル崩壊と失われた10年・・・。日本経済全体が低迷する中、カゴメも例外ではなかった。デフレの波はカゴメを直撃。激しい価格競争で営業利益率は低下。まさに会社の存亡危機だった。そうした中、社長に就任したのが喜岡浩二社長である。喜岡社長は1964年にカゴメに入社、営業・宣伝・経営企画など様々な経験をしてきた人だ。社長に就任すると早速、構造改革に着手。「売上が落ちてもいいから価格を是正しろ!」との大号令のもと、1本あたり10円から20円の値上げを断行した。最初の6か月間は売上が2割も減少し、「胃の痛い日々」が続いたが、その後、売上は見事な回復を遂げた。 
値上げしたにも関わらず売上を伸ばすことができた背景には、品質の良いものは必ず消費者に受け入れられるという強い自信があった。カゴメは年間4億本のトマトジュースを生産しているが、その材料は全て契約農家で生産された野菜で、新鮮さを失わないうちに加工している。野菜はねじり、繊維とジュースを効率よく分け、うまみを損なわないように高速で絞り出す。もちろん添加物は一切使われていない。このように「原材料から加工、流通までを創業以来すべて自社で一貫して行っていることで高品質を保っている」と喜岡社長は自信を覗かせる。 
カゴメは生鮮トマト事業にも本格参入しようとしている。世界にトマトの種類は8000種もあると言われるが、そのうちカゴメは6500種類もの種子を所有している。その豊富なストックを生かして1997年から生鮮トマト事業を全国8か所で展開している。「ハイテクを駆使した大型菜園」で、栽培は全てコンピューター管理されている。こうした「株式会社の農業参入」に対して、農業関連者からは反発の声が絶えず聞かれるが、喜岡社長は「現在の農地法は農家を守るものであって農業を守るのもではない。時代遅れで難解な法律だ」という。さらに「これでは農業への新規参入は難しく、高齢化が進む日本の農業に若い人は入ってこない」との懸念を示した。 カゴメというと個人株主作りへの積極的な取り組みでも知られている。『開かれた企業』を目指し、2001年から個人株主10万人計画を進めてきている。「カゴメにとって株主と顧客は表裏一体。個人株主を増やすのが王道」との考えのもと、株主総会では個人株主を立食パーティー形式の試食会に招待するなど、カゴメならではのイベントを実施してきている。その結果、個人株主数は8万7000人を超えた。内訳をみても約50%が女性で、そのうち主婦が36%を占めるという。カゴメの企業理念を理解し、カゴメの商品を支持する個人株主の存在は、結果的に有効な買収防衛策とも言えそうだ。 |
|
||||||||||
|
||||||||||