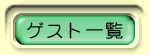| 第185回 2004年7月3日放送 
2004年3月期の決算で17期ぶりの復配を果たした井関農機。番組冒頭で「ホッとした。やっと先が見えてきたと思った」と正直な感想を漏らしていたのが中野弘之社長だ。
井関農機は大正15年に創立されたトラクターやコンバインなどを製造する総合農機メーカーである。しかし、ここ10数年間、業績は低迷を余儀なくされてきた。その大きな要因は農家数の減少で農機の需要も減っているためだ。中野社長が入社した1962年当時は日本人の4割程度が農業に携わってきたが、年々その数は減少し、去年の農家戸数は298万戸と300万戸を割り込んでしまった。毎年2%ずつ減少してきているという。さらに景気の低迷も重なって、平均10年に1度という農機の買い替え需要も停滞していた。
 中野さんが社長に就任したのは2001年。井関農機は4期連続で赤字を計上するなど、まさに一番苦しい時だったが、「これが最後のチャンスだ。何としても3年のうちに復配する。そのためには生産効率を上げ、企業体質を変える!」と心に決め、思い切った構造改革を断行。そして見事に業績を急回復させた。 中野さんが社長に就任したのは2001年。井関農機は4期連続で赤字を計上するなど、まさに一番苦しい時だったが、「これが最後のチャンスだ。何としても3年のうちに復配する。そのためには生産効率を上げ、企業体質を変える!」と心に決め、思い切った構造改革を断行。そして見事に業績を急回復させた。
売上が減少傾向にある中での構造改革は、徹底してコストダウンを図ること。どのような状況にあっても利益を出せる体質作りが至上命題だった。そこで取り組んだのが生産ラインの効率化だった。そもそも日本の農地は地形も土質も多岐に渡っているため、それに対応する農機の生産も、一機種あたりの生産台数は少ないが、種類は数百種にも及ぶという典型的な多種少量生産だ。なかには年間に10台も生産しない機種もあるそうだ。
そこで井関農機は、独自の生産システムである「混合生産方式」の更なる効率化を進めた。この方式はトヨタのカンバン方式を参考にしたものだが、井関流に改良を重ねたもので、種類や型式、色など異なる農機が1台1台、1つの生産ライン上を流れていく仕組みである。これによって注文から僅か2週間で納品が可能になるなど、納期の大幅な短縮化と過剰在庫の削減に成功した。さらに「部品の一体化」も徹底して進めたほか、発想の転換による「設計の抜本的な見直し」などによって、新製品の生産コストを30%も削減することに成功した。
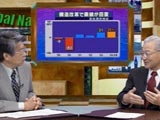 こうした謂わば「守りの経営」で成果を上げた井関農機は、いま「攻めの経営」に転じようとしている。最も力を入れているのが新型トラクターの販売だ。農機のフルモデル・チェンジは約10年に1度のこと。今年、井関農機が社運を賭けて投入したのが新型トラクター「ジアスAT」である。人気のキャビン付きでエアコンやオーディオ完備は当たり前。操縦もいたって簡単で、自動車免許があれば誰でも運転できるという。さらにトラクター自体が前回の作業スピードなどを記憶しておくメモリー機能が備わっているため、1年後でもボタン1つで同じ作業を繰り返してくれるなど高齢者にも配慮した、まさに「画期的な新商品だ」と中野社長も満足そうだ。 こうした謂わば「守りの経営」で成果を上げた井関農機は、いま「攻めの経営」に転じようとしている。最も力を入れているのが新型トラクターの販売だ。農機のフルモデル・チェンジは約10年に1度のこと。今年、井関農機が社運を賭けて投入したのが新型トラクター「ジアスAT」である。人気のキャビン付きでエアコンやオーディオ完備は当たり前。操縦もいたって簡単で、自動車免許があれば誰でも運転できるという。さらにトラクター自体が前回の作業スピードなどを記憶しておくメモリー機能が備わっているため、1年後でもボタン1つで同じ作業を繰り返してくれるなど高齢者にも配慮した、まさに「画期的な新商品だ」と中野社長も満足そうだ。
こうした新製品を生み出す背景には、井関農機が創業以来大事にしてきた「新技術へのこだわり」がある。社内から毎年1万5000件もの発明提案が上がってきて、そのうち4分の1は実際の特許取得や新製品開発に結びついているという。多い人では年間700件も発明提案を出してくるそうだ。
 注目される次の一手だが、井関が力を入れているのが海外と新規分野の拡大である。海外売上高はまだ全体の1割未満だが、中野社長は今、中国市場に大きな可能性を感じている。中国の農作物の作付面積は日本の32倍もあるが、農機の普及台数はトラクターで日本の半分、コンバインでは5分の1でしかない。潜在需要は膨大だ。そこで去年、中国常州に工場を設立、今年からコンバインの現地生産を開始した。 注目される次の一手だが、井関が力を入れているのが海外と新規分野の拡大である。海外売上高はまだ全体の1割未満だが、中野社長は今、中国市場に大きな可能性を感じている。中国の農作物の作付面積は日本の32倍もあるが、農機の普及台数はトラクターで日本の半分、コンバインでは5分の1でしかない。潜在需要は膨大だ。そこで去年、中国常州に工場を設立、今年からコンバインの現地生産を開始した。
一方、新規分野の拡大については「養液栽培システム」の販売に力を入れている。東京ドームの半分ほどの広大な施設の中で、温度や湿度、さらには二酸化炭素や肥料の濃度をコンピューターで完全自動管理。生産性はハウス栽培の2倍、露地栽培の4倍と高いうえに、農薬を使わないため安全性にも優れ、さらに出荷時期を自由にコントロールできるため市況を睨みながらの生産も可能だ。日常の管理に人手はほとんど不要など、まさに「野菜の工場」であるこの養液栽培システムの販売拡大に大きな期待を寄せている。
株式会社による農業への参入問題が議論されるなど、日本の農業は大きな転換点を迎えていると言われるが、井関農機は新しい農業のあり方を提案することで新規分野の拡大を図り、「農機の井関」から「農家の井関」へと変貌して行きたいと中野社長は強調した。 |