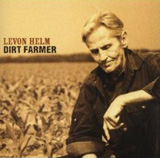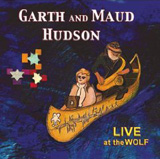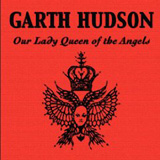#33 「ザ・ウェイト」ザ・バンド

出演者
- リーヴォン・ヘルム
- ジョン・サイモン
- ガース・ハドソン
- ジム・ウィーダー
- ピーター・バラカン
放送内容
ザ・バンド。
「アメリカそのもの」と讃えられるサウンドを持つ、唯一無二のグループ。
カントリー、ゴスペル、R&Bといった様々な音楽の豊かな響きがロックのもとに渾然一体となった彼らの音は、サイケ全盛の60年代に、大きな衝撃をもって迎えられた。
ミュージシャンズ・ミュージシャンとしていまなお多くのアーティストからのリスペクトを集めるザ・バンドの代表曲といえる「ザ・ウェイト」。
そこには深遠な音楽の謎と、尽きせぬ味わいがある。
番組では、ザ・バンドのメンバーであるリヴォン・ヘルムとガース・ハドソンに取材。
『ラスト・ワルツ』から30年以上を経た現在もなお理想の音楽を追い求める彼らの姿を、最新のライヴ映像と共に紹介する。
出演:リヴォン・ヘルム/ガース・ハドソン/ジョン・サイモン/ピーター・バラカン
ディレクターによる取材ウラ話
ザ・バンド。
こんなに魅力的かつ難しいお題は、そうそうあるものではありません。
孤高。深遠。厳格さとカオス。神秘。宿命。
音から滲んでくる、胸がかきむしられるような感銘。
この音楽を前に、TV番組は一体何ができるのでしょう?
そして。
取材に向かったウッドストックでは、
まさに予想に倍する濃密な世界が待っていたのでした。
—————— ・ ——————

まずインタビューに訪れたのは、ジョン・サイモン師の御自宅。
ウッドストックから1時間ほど離れた山の上。渋くて落ち着く木造りの家。
ピアノのあるリヴィングでは、
一体どれだけのミュージシャンが集い、語り、音楽を練り上げたことでしょう。
「仕事の前には、まずお茶だ。」と、サイモン師が自らお茶を煎れてくださる。
何種類ものハーブティーを揃えて、時々の気分で楽しんでいるとのこと。
あんな洒脱であたたかい音楽を作る人は、やはりハーブティーなんだ、と思わず感銘。
出されたお茶は重めの香り。それが窓の外の雨模様と、完璧なマッチング。
ううむ、マエストロはその全てが徹底してマエストロです。
都会では背伸びして聞こえるオーガニックという言葉が、
ここではありのままに感じられます。
ハーブティーはおいしくて、
何故か幼少の頃 夏の暑い日に食べたスイカを思い出す。
とても人間らしい暮らしを感じる。フィジカルで、なおかつ精神性が高い。
ウッドストックのマジックを体で感じたような気がした瞬間です。
—————— ・ ——————
ガース・ハドソンは決して時間通りにはやってこない。
誰もがそう言いました。
夜7時にはインタビュー場所のスタジオに来るとのことでしたが、
スタジオのオーナーは、どんなに早くても10時だろうと言います。
レコーディングセッションの時は、登場はだいたい深夜の12時。
丑三つ時になってようやく音を合わせ始める、という
「極めてミュージシャンらしい体内時計を持っている」のだそうです。
はたして。

ガースがやってきたのは7時15分。
我々と一緒にいたジョン・サイモンと楽しそうに旧交を温めたのち、
8時前にはインタビューが始まりました。
スタジオのオーナーは「奇跡だ…」と茫然。まるで映画みたいです。
そして、ガースは言いました。
「まずピアノを弾く。そこからオーバーラップして、私が語り始める。そうするように。」
そうしました。仰せの通り。
だから番組でいきなり弾き始めるピアノは、
ガースが「自分の話の前に必要な音」として弾いたものです。
あれ以外にも、実に30近いパターンを次々に弾きまくり、そして言いました。
「どれを使っても良い。任せる。」
バッハのコラールが如何に完璧であり、研究されるべきものであるか。
ポール・サイモンは、どのようにして賛美歌から「アメリカの歌」を生み出したのか。
ジャンプ、スウィング、初期のR&B、ヒルビリー。
ギターが電気化する以前の、ソロ楽器としてのサックスの重要性・・・・・。
縦横に語り続けるガース。
スタジオのオーナーは、夕食の出前が冷めていくのを
ただ見つめているしかありませんでした。
インタビューが終わり、一同が出前のパスタをレンジでチンして食べたのは
午前2時近く。
深夜の静寂の中で食卓を囲み、静かに音楽を語りながら食事をとるガースの姿に、
やはり丑三つ時が似合う人だと深く感じ入ります。
午前3時。海よりも深い感謝を込めたささやかな菓子折をお渡しして深礼。
ガースは優しく笑うと、その紙袋を まるで御神体みたいに丁寧に車の後部座席に置くと、
ゆっくりと車のエンジンをかけて去っていきました。
—————— ・ ——————
翌日は、リーヴォン・ヘルム・スタジオでの取材。
リーヴォンの自宅兼スタジオである巨大なログハウスは、
その夜行われる「ミッドナイト・ランブル」という定期ライヴの準備で
ごったがえしていました。
スタジオのスタッフは皆 もの凄く熱意に溢れていて、
リーヴォンが如何にリスペクトを集めているかが伝わってきます。
ライヴは、
夜8時からケヴィン・ベーコンのThe Bacon Brothersで始まり、
9時半からThe Levon Helm Bandが登場。終了は深夜12時過ぎ。
2時間半も休憩無しで演奏し続けるリーヴォンのパワーに、
狭い会場は親密かつ怒濤の盛り上がりを見せました。

ディレクターの僕も、この日は久々に小型カメラを手に撮影。全員野球です。
最前列端に小さくなっての撮影でしたが、
もう、あまりに演奏が素晴らしいのでカメラ回しながら涙がノンストップ状態。
ホーンセクションの皆様はその異様な東洋人を見て呆れながらも、更に発奮したそうです。
ピアノの人がやたらカッコイイな、と思っていたら、
ソロの後で「ドナルド・フェイゲンに拍手を!」と紹介されています。
まさか。そんな。毎回のように大物が飛び入りするとは聞いていましたが…。
よく見ると、ホントにドナルド・フェイゲン。
気づきませんでした。こんな3〜4mの距離で見たことなどないし。
King Harvest など数曲ではフェイゲン氏がリードヴォーカルも。
目の前で起きていることが信じられません。
一方、リーヴォンのすぐ脇から撮影していたカメラマンは、元ドラマー。
ライヴ終了後はすっかり骨抜きのパンチドランカー状態。
茫然と「魂のスネアだ…」と繰り返すばかり。
あんな物凄いライヴがあたりまえのように繰り広げられているとは。
リーヴォン、そしてウッドストック。本当に本当に、底知れないです。心底驚きました。
リーヴォンは、演奏後のインタビューにも応えてくれました。
『わたしが子供の頃は、レコードは聞かなかった。
ジュークボックスが一番の音楽供給源だった。
本当に美しかったし、サウンドも素晴らしかった。
父親と町に出た時は、小銭をもらってジュークボックスの傍に座り、
聞いたこともないようなサウンドに ずっと耳を澄ましていた。』
…感動しました。リリアン・ギッシュの自伝を思い起こさせる感動。
でも残念ながらこの部分は、編集上、カットせざるを得ませんでした。
だからここに書きました。もったいない。けど仕方ない。
他にも、全てをお見せしたいものばかり。
特にライヴ・シーン。
“私たちのやってきた音楽について知りたかったら、
何よりも今の私たちの演奏を聴いてもらうのが一番だ。”と、
リーヴォンは我々の番組のために8曲も撮影許可を出してくれたのです。
OPHELIA、SAME THING、DRAWN IN MY OWN TEARS、
LONG BLACK VEIL、GOT ME A WOMAN、ANNA LEE、
そしてRAG MAMA RAG、THE WEIGHT。 どれも最高。
ザ・バンドの音楽が時を越えて人の心を惹きつけるその理由を、
この演奏が何よりも雄弁に語っています。
いつの日か、この貴重な映像を蔵出しして、
ゆったりとフルレングスで 皆様にお届けするチャンスが来ますようにと、
わたくし、天に祈っております。
そして、リーヴォンは何度も言いました。
「日本のオーディエンスは最高だった。また日本でプレイしたい。」
かつての日本ツアーは、本当に忘れ難い思い出となっているそうです。
天の神様、来日の実現も、よろしくお願い致します。祈願。
PLAY LIST
- ザ・ウェイト/ザ・バンド
関連商品:Music From Big Pink/ザ・バンド - 怒りの涙/ザ・バンド
関連商品:Music From Big Pink/ザ・バンド - ME DON'T LOVE YOU/ザ・ホークス
関連商品:ザ・バンド・ボックス ミュージカル・ヒストリー/ザ・バンド - ヤズー・ストリート・スキャンダル/ボブ・ディラン
関連商品:地下室/ボブ・ディラン